このコーナーでは制作会社に勤めるクリエイターが普段何を読んで学び、どんなことを実践に生かしているのかを紹介していきます。
記念すべき第一回目にインタビューしたのはフロントエンジニア二年目のみなくん!
みなくんは文系出身で独学でフロントエンドを学ばれてきたそうです。
そんなみなくんに揚羽の業務で特に役に立った本を選出していただきました。
フロントエンド専門制作会社が教える速く正確なWeb制作のための実践的メソッド ワークフロー構築、コーディング規約、制作&ディレクションTipsなど、高品質な制作を支える現場の仕事術
https://www.amazon.co.jp/dp/4839960968
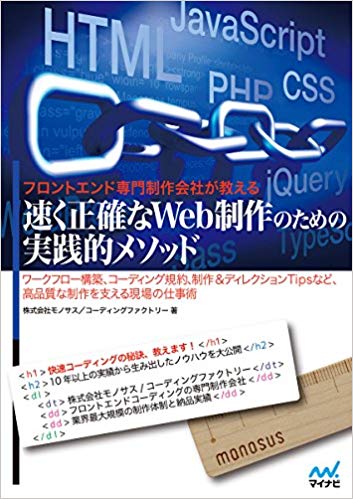
モノサス コーディングファクトリー/著
出版社名 マイナビ出版
出版年月 2017年5月
ISBNコード 978-4-8399-6096-4
(4-8399-6096-8)
税込価格 2,646円
頁数・縦 233P 26cm
まずはみなくんについて少しお伺いさせて下さい。
なぜ独学で勉強されていたのでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーー
勉強した理由を一言で言ってしまうと、手に職を付けるためです。(笑)
小学5年生の時にHTMLを触ったのがが僕のコーディングスタートになります。
そこから地味にサイトを作ったりして…
同じ高校のバンドの携帯のサイト作ったり、大学のサークルのHP、知り合いのミュージシャンのサイト、友達経由で友達の友達のサイト等々知人経由でサイトを作ってあげていました。
趣味の延長なので無償で作っていましたね。
無償でなんて、作ってもらった人はラッキーですね!
その経験を生かして就職活動もされたのでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーー
実は公務員を目指していたんです。
でも、駄目になってしまって、、、
さぁ、次は何をしようと考えた時に「そういえば、サイト作ってたな」って思い出して
デザインとコーディングどっちに進もうか迷ったんですが
デザインに関しては勉強はまだまだだなと思ってコーダーの道に進んでみようかなと思い行動していました。
消去法なんですね(笑)
本格的にいつからコーダーとして活動されていたのでしょう?ーーーーーーーーーーーーーーー
大学を休職していたのですが、その時に制作会社のインターンとして活動していました。
でも、その会社が超ブラックで(笑)入社したタイミングで正社員が誰もいなくてインターン生+社長というメンバーでした。そこで一番コードが書けたのが僕だったこともありリーダーを任されていました。
入社した会社がブラックだったって漫画みたいな話ですね・・・・ーーーーーーーーーーー
そうなんです。リーダーということもあり他のインターン生より仕事は多かったですがなぜか責任感が芽生えちゃって、『通勤中に仕事→出社→終電→終電の中でも仕事』という生活を送っていました。そんな生活が続いて入社6ヶ月目で倒れました。あ、因みに日給5,000円&交通費無しっていうところもブラックに拍車をかけてますよね。
でも、そんな生活でも楽しかったんです。で、「これは天職かもしれない!」と思いました。
これがコーダーを目指すきっかけでもありました。
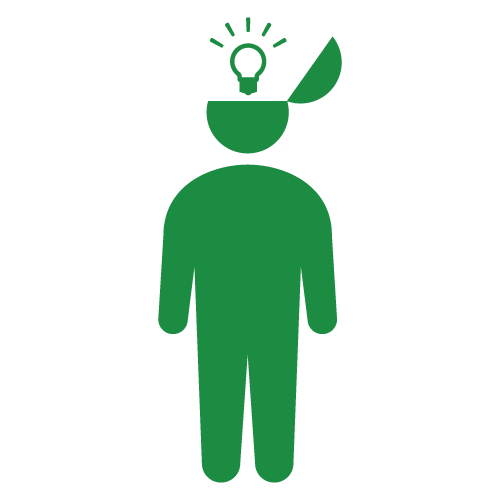
気づきのきっかけが凄い(汗)
そこから何社か経験されて揚羽に入社したと聞きましたがーーーーーーーーーーーーーーー
そうですね。そこからは2社制作会社を経験しています。直近の前社ではきちんとした制作会社だったので様々な企業の事例を見ることができたのはいい経験でした。でも、そんなしっかりした制作会社でもコーディングの指針はなくて皆独自に設計していました。
そんな中、あの有名なコーディングファクトリーからコーディングの本が出るとわかって飛びつきましたね!
なるほどなるほど。(あ、ついにブックレビューの話に突入しそう・・・!)
力強いタイトルですが、こちらどんな本になりますか?ーーーーーーーーーーーーーーー
フロントエンド専門の制作会社であるコーディングファクトリーの書籍で、
現場での経験から得たノウハウを解説された本です。
コーディングする際に癖や好みが出るポイントを漏れなくカバーしており、
コーディングに指針がほしい方におすすめしたいです。
この書籍は、一人でフロントエンドを学んでいたときからお世話になっていた書籍で、
ディレクトリ構造・HTML, CSS, JS 等の命名規則からワークフローまで真似て学んでいました。
コーディングに指針がないとどうなるのでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーー
コーディングの際にルールが決められていないと、自分以外の人が関わった時に解析する手間が
かかったり、意図しないところでレイアウトが崩れたり、考える時間がかかったりするので、無駄が発生し、クオリティが下がる場合がほとんどです。限られたスケジュールで案件を進めるには、コーディングのガイドラインが必須です。
それは困りますね、、、
そんな中、この本に求めていたものはなんだったのでしょうーーーーーーーーーーーーーーー
そうですね。僕自身も結構苦労しました。
それと、大学生の時にサイト作っている内に「あれ?僕はこう書いてみたけど、これ、みんなどうやっているの・・・?何が正解なの?」って思うこと正直あってフロントエンドが書いている指針なら信用できるなって思いもあり手に取りました。それまで色んな本は読んでいましたが読み終わって「結局、どうするの?」みたいなこともあったので、信頼できる本に出会えたことはとても良かったです。
インプットすることはできてもどうアウトプットするのか、それが本当に正しいのか不安になることって確かにありますよね。
では、この本を読んでどんな点を仕事に活かしているのでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーー
揚羽でも画像ファイルの命名ルールの策定や、作成したページをチェックする際のポイント等をワークフローに取り入れさせていただいてます。
また、揚羽にインターンシップに来ている学生にもこの本を読んで実践してもらっています。
インターンシップに来ている学生さんにも読まれているのですね!
チェックのポイントが描いてあるので、先輩に聞くことなく自分でできるのでより成長に繋がりますね。
では、みなくんはどんな人が読むべきだと思いますか?ーーーーーーーーーーーーーーー
主にワークフローについて書かれている本なので、
HTML, CSS, JS 等の知識は前提として持っているものとして書かれています。
なので全くの初心者の方が手に取るような本ではありません。
また、CSSの設計がコーディングファクトリー様独自の設計思想(OOCSSとSMACSSを組み合わせたもの)なので、会社や案件によっては使いづらいかもしれません。
では、自分でコーディングをした経験がある人がターゲットになってくるんですね。
みなくんありがとうございました!!
終わりにーーーーーーーーーーーーーーー
みなさん、いかがでしたでしょうか?
フロントエンジニアとして第一線で活躍しているみなくんだけでなく、インターンシップで来ている学生さんにも役に立っている一冊。
この記事がフロントエンドエンジニアを目指す方、目指している方などの参考になってほしいです。
