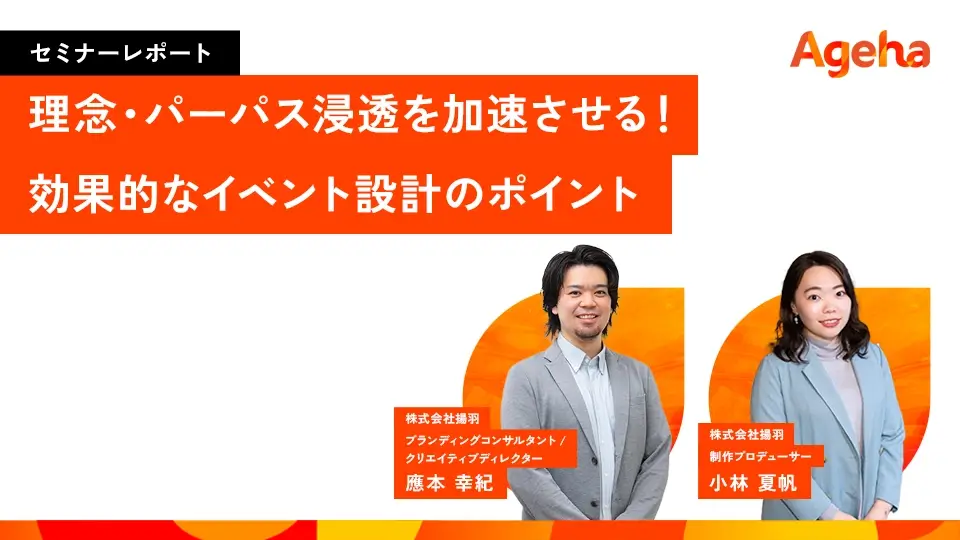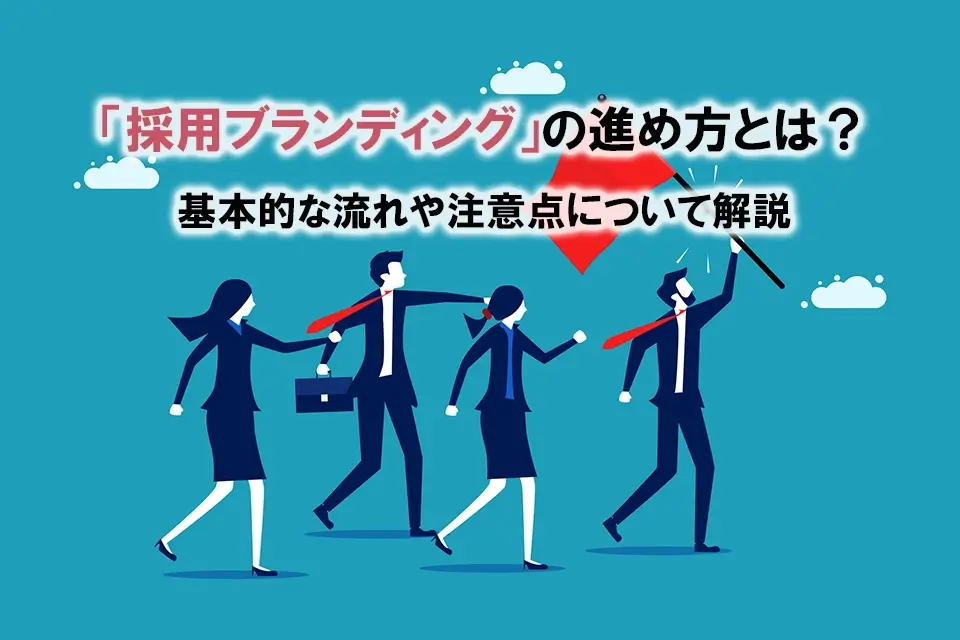オンラインセミナー:Z世代はSDGsとどう向き合っているのか?~
皆様、こんにちは。営業企画部の石田です。
一瞬夏の暑さを思い出したところで、あっという間に梅雨の時期になりました。しばらく雨の日が続きそうですが、密は避けつつ、紫陽花などこの時期ならではの出会いを楽しみたいと思います。
さて、先日5月12日(水)に、「Z世代はSDGsとどう向き合っているのか?」と題したセミナーを開催いたしました。
現役の大学教授でありながら、企業がSDGsを経営に取り入れるコンサルティングを行っている眞鍋 和博氏をゲストにお招きし、「Z世代」の視点からの「SDGs」について徹底解説しました。

スピーカー:黒田 天兵
株式会社揚羽
インナーブランディング研究室 室長
SDGsトランスフォーメーション推進室 室長

スピーカー:眞鍋 和博 氏
公立大学法人 北九州市立大学 教授
サステナブル北九州 代表
イントロダクション
揚羽では、これまで採用・インナー・アウターブランディングを通し企業のらしさを本質的に伝えるお手伝いをしてきましたが、これからは社会全体の課題を考慮していかなければいけないと考えています。
これからは、世界が認識する社会課題、つまりSDGsに対して、どう貢献していくかを定義する必要性が高まっていきます。
求職者・社員・顧客・投資家、全ての領域においてSDGsとどう向き合っていくか大事になる中、今回テーマにしたいのは、採用ターゲットとなる今後の未来を担う「学生/若者」です。
今回は、3つのパートに分けて、今後の未来を担うことになるミレニアル世代やZ世代が、SDGsにどんな考えを持っているのかお話いただきました。
若年者とサスティナビリティ
まずは、各調査データから学生/若者の「社会貢献」に対する関心の高さをご説明いただきました。
・SDGsに対する認知度は若い人ほど高い傾向。
・若い層は行動に対するハードルが低い。年齢が上がる程「SDGsについて、自分で何か行うにはハードルが高い」と答えている。
(株式会社電通「第4回SDGsに関する生活者調査」より)
・学生の就職先企業に決めた理由は「社会貢献度が高い」が3年連続1位。
・学生は、企業理念で「社会貢献度」を判断している。
(株式会社ディスコ「就活生の企業選びとSDGsに関する調査」より)
実際に就活中の学生の話を聞くと、SDGsに取り組んでいるかどうかをWebサイトでまず見るそうです。さらに、特に意識が高い学生は、その会社が既に行っている社会貢献活動に表面的にSDGsの番号を振っているだけではないかという点まで見ているとのことです。
「若者の世代観」という点では、ミレニアル世代やZ世代は大半を不景気のなかで過ごし激変する社会の中で育ったため、上の世代とは異なる価値観を持つ傾向にあるとのことです。リーマンショックや大規模な自然災害など「何が起こるか分からない」時代に育ったからこそ、「何かしら自分ができることをやりたい」という感性があるようです。
ミレニアル世代とZ世代は共に社会貢献に親和性が高くなってきていると言えます。
学校教育とESD/SDGs
次に、学校教育の現状から、学生の「持続可能な社会」への理解についてお話いただきました。
実はSDGsより前から、ESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)は国際社会で行われていたそうです。ESDとは、持続可能性にかかわる様々な主題を様々な立ち位置で総合的に学んでいこうという学習の領域のことを指し、創造力を育むことを目的とされていました。ESDは、2002年の世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)にて日本が提案したもので、日本の学校教育にも取り入れられたそうです。
その後、SDGsの目標4にESDが組み込まれましたが、2019年からは「17個全てのゴールの達成を推進する人材を育てることがESD」というESD for2030が採択されています。
日本においては、2020年~22年度に改訂される新学習指導要領に変化が起こっています。前文の中に「持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と明記されていたり、総合的な学習の時間が「総合的な探求の時間」に変更されていたりします。「総合的な探求の時間」では、課題の設定・情報の収集~整理分析・まとめ表現することをチームで行い、よりよい社会をつくることを学びます。
さらには、英語や理科や家庭科の教科書にもSDGsが取り込まれ、SDGs自体を学ぶだけでなく「SDGsをテーマに学ぶ」時代になっているそうです。
今後は、「SDGsネイティブ」と呼ばれる人材が世に出ていくような時代に変わっている、ということを前提に物事を考えていく必要があると言えます。
SDGs時代に求められる思考
最後に、そんなSDGs時代に求められる思考様式を4つ、解説いただきました。
アウトサイド・イン
これまでは、「顧客が求めるものに商品サービスを提供」していたところ、今後は「社会が求めるものを商品サービスにし、顧客を誘導する」ことが必要となります。お客様目線でなく、社会目線でニーズを捉えていくことが大切です。そのためにも、会社として外の世界を知る機会をいかにつくるかがポイントとなってくるとのことです。
バックキャスティング
日本人が得意とするのは、「今年100%達成したので、来年は110%」といったフォアキャスティング(改善)の思考と言われています。SDGs時代に求められているのは、「ムーンショット(目指すべき姿)を掲げ、そこからバックキャスト(逆算)していま何すべきかを考える」といった逆算の思考とのことです。
トレード・オフ
トレードオフは「両立できない関係」という意味を持ちますが、ここで重要なのはトレードオフそのものではなく、「トレードオフにならないようにしなければならない」という思考とのこと。自社の利益のみを考えるのではなく、誰一人取り残さないビジネスをいかに実現できるかが重要です。日本でいう「三方良し」は、まさにこの思考を指しています。
デザインシンキング
デザイン思考・アート思考といったように、今までと異なる確度から物事を見て、価値観を変えていこうという考えです。これまで重視されていなかった思考法を、経営や日々の仕事の中にどのように取り入れて発揮していけるかが求められています。
まとめ
今回、3つのパートでは下記内容をお話いただきました。
①ミレニアル世代、Z世代は共に「社会貢献」に親和性が高くなってきている。
②SDGsの教育は当たり前の時代に。SDGsネイティブが活躍する社会に。
③これまでと全く見方を変えることが大切。新しい価値観を日々の仕事の中にどう取り入れていけるかがポイントとなる。
以上、5月12日(水)開催オンラインセミナー~Z世代はSDGsとどう向き合っているのか?~のセミナーレポートでした。
SDGsに関する取り組みや採用活動にお悩みの方は下記ご相談窓口からご相談ください。課題に合わせた実際の施策事例などもご紹介させていただきます。
今後も弊社独自のネットワークやノウハウを活かしながら、皆さまのお悩みを解消できるようなセミナーを随時開催していきますのでご期待ください。